「One Kitchen」オーナー 原崎 拓也さん インタビュー
~one kitchenを作った経緯と日本のコミュニケーションのあり方~
one love, one people, one kitchen.
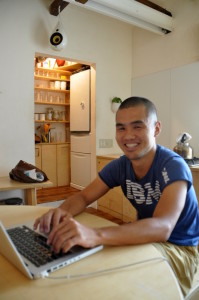
原崎卓也(34)さんはキッチン付きレンタル コミュニティースペース「One kitchen(ワンキッチン)」を東京の四ツ谷で経営している。
設計から施工まで、友人達の協力も得つつ、ほぼ全部原崎さん自身で仕上げたの内装は、天然素材がふんだんに使われ、円を基調としたデザインは場の一体感をより引き立ててくれる。
ワンキッチンではイベント、ワークショップなど様々な催しが日夜開かれている。
原崎さんは20代の頃に世界中40ヶ国以上を旅し、環境問題やコミュニティのあり方への関心をもつようになった。
”旅先で見た大自然を未来の子ども達へ残したい”
その後、アジア諸国の環境問題に取り組むいくつかNGOを巡り活動に参加し、活動を通じて環境問題の原因を追求していくと、彼はひとつの答えにたどり着いた。
”様々な環境問題の原因はその土地ではなく、その資源を輸入している日本などの消費国にある”
日本の資本優先の大量消費社会は沢山のゴミと無駄を出し、自給率の低い日本は間接的に、他国の自然を破壊してしまっている。
例えば、東南アジアの原生林から伐採された木材の輸出先は、日本がダントツで一番多い。
帰国後、日本人のあり方、日本の社会の根本的な問題を考える上で、自分なりの問題へのアプローチとしてOne Kitchenのプロジェクトをスタートした。
-ワンキッチンをつくった経緯とコミュニケーションについて-
”旅先の宿や10年くらい前から少し前までシェアハウスに住んでいた頃に、皆でご飯をつくって食べる機会にたくさん恵まれました。
「一番ベーシックで一番大切な人の集まりは、一緒にご飯を作って食べること。」
みんなでご飯をつくって、一緒にご飯を食べる、このキッチンでの一連のやり取りのなかで一体感のあるコミュニケーションが取れるんです。
だから「究極のコミュニケーションの場はキッチンにある」と思ったんです。
今の社会はいき過ぎた個人主義社会で、みんなコミュニケーションをとるのが下手になったんじゃないかな、それが原因で人間関係が崩れている。
キッチンでされるような、シンプルだけど大切なコミュニケーションが都会の日本人には出来ていないと思うんです。
シェアキッチンのような場の体験を一般の人たちにも経験して欲しくて・・・、そしたらもっと密なコミュニケーションが取れて、人間関係が良くなるっていくんじゃないかな・・・。
そうしたらもっとみんなが暮らしやすい社会になっていくんじゃないかなと思うんです。
今でこそ、シェアハウスが世間で認知されてきましたが、まだまだ一般の人にはそれを経験する場があまりないと思います。
地価の高い都会で一般の人には10人以上で集まれるスペースが中々もてないんですよね。
それなら自分でそういう場所を作ればいいと思って、2010年からOne Kitchenのプロジェクトをスタートしました。
ワンキッチンはそういうコミュニケーションの場をビジネスという形で取り戻す、第一歩なんです。”
-将来の理想のコミュニティーのビジョンはどのようなものですか?-
”僕の将来のビジョンは100人ぐらいで暮らすコミュニティーですね。それくらいなら携帯電話も使わなくていいし。
たぶん、人間って100人くらいの人までしかちゃんと感情をもって扱えないと思うんです。
情報量としては1000人を脳では解析出来たとしても、それほどたくさんの人の感情を感じられる感受性はないと思うんです。
そうなると、そこには目に見えない、感情を感じきれない人たちが出てきて、その人たちの感情を無視してしまう・・・
そうすると互いに傷つけあったり、争いが生まれたりすると思うんです。
だからコミュニティーは本当は100人くらいの規模がいいんだろと思うけど、もし人類がそれに到達するには何千年もかかるでしょうね。
自分の中ではその段階に行けるだろうけど、今は別に行かなくていいと思っています。
今はそういったコミュニティーの繋がりをつくる過程で何か出来ればいいと思ってます。あんまり大げさなことは考えてませんが・・・。”
-100人くらいの仲間内でお金を介さずに暮らしていけるような場所をつくるということですか?-
”そうですね、そういうコミュニティーを少しずつつくりたいです。
その上でもう少しみんなが企業というものから離れて、自分で自立して仕事が出来たりとか、物事を自分で考えたり、自分のコミュニティーを持ったりするのが、ひとつの段階なのかな。
けど今のでっかい社会、世界中の人が繋がって生きている経済原理みたいなものと小さいコミュニティーとを完全には分離することは出来ません・・・。
どうしても、両方が入り混じった次元で生きて行かないといけないと思うし、それがとうぶんは妥当なやり方だと思います。
片方により過ぎちゃうとその反動を受けるから、バランスが大事ですね。
だから社会からの自立に向かって、みんながもう少しクリエーションして、個人事業したり、自分で考えられる人が増えていけばいいのかな。
たぶん、いつの時代もどこにいっても、不安や不満は人はあるから、その不安や不満に対して自分が行動していれば、人はより良いもの手に入れられるんじゃないかなと思います。
それぞれの人生の方向が分かってきて、その方向に向かっていける方法論をみんなが分かっていくのが重要。ただ方向だけ示してもだめで・・・。
だからみんなが自分の方向に向かっていくのをお互いに方法論をシェアしたりしてサポートしていけば、いいんじゃないかな。
そしたら、もっと良い世の中になっていくと思います。”
-コミュニティーワークをする上で何か注意点はありますか?-
”ビジネスとコミュニティーワークの明確な線引きが難しいんですけど、重要ですね。
自分でビジネスを始めて徐々に分かってきましたけど、
one kitchenを運営する際に、対お客さんは僕のビジネス構想で、コミュニティーワークである友達の間ではお金を介入しないことにしています。
自分と近い感覚で活動している色んな人を見てきましたけど、やっぱりコミュニティーワークではお金を生み出すのは駄目だと思いましたね。
今はどこからお金にしていいのかを自分できっぱり分けれるようになったと思います。
ミクシーとかフェイスブックとかのSNSでビジネスしてる人もいますけど、やっぱりそこでも自分のソーシャルとビジネスの線引きが難しいですよね。
ミクシーがビジネスっぽい色が濃くなったから、みんなが辞めていったひとつの理由だと思いますし。”
- – – – – – – – – – – – – – – - – – – -
原崎さんはまさに「think globally act locally」を体現されている。
世界で様々な問題を実際に見てきて、それに対して自分で出来るアクションとして、コミュニケーションの場を提供するという形で。
彼の創造性と行動力は旅で長く束縛のない社会にいたときに培われたものだろう。
旅人は旅を終えた後、中々社会とのバランスを取るのが難しいが、彼はしっかりと現代の社会構造を把握しつつ、自分の個性を活かし世の中へ働きかけている。
原崎さんの言う、コミュニティーワークにお金を介入しないというのはまさに、※「友産友消」という概念に近いのではないだろうか。
(※友達が生産したものを友達が消費する。地産地消よりも更に密なコミュニティー構造。)
資本主義社会ではどうしても、お金を持つものがより裕福に、そして貧しいものはより貧乏になる。
だから、コミュニティー内でお金を介さないでするやりとりから、資本主義社会から自立でき、より平等な社会が形成されるであろう。
ただ、現在の社会に生きる上では彼の言う通り、社会とのバランスをとることが重要だ。
資本主義社会からの自立の一歩として、家庭菜園を始めたり、様々なDIYに挑戦するのもありだろう。
単に今の社会を否定するのでなく、みんなが楽しみつつ自立していけば、今の価値観と違う新しい楽しい社会が生まれるのではないだろうか。
原崎さんのような人たちからコミュニティーの輪が広がり・・・
クリエイティブでみんなが共生出来る 平和な世の中の訪れもそう遠くはないだろう。
みなさんもone kitchenを利用して究極のコミュニケーションを体験してみませんか?
みんなでつくるクリエイティブな空間であなたは新しい気付きが得られるかもしれない。
詳しくはこちらOne Kitchen HP→http://onekitchen.jp/

原崎拓也(はらさき たくや)
1980年生まれ、静岡県出身。
高校卒業後、一年浪人生活し受験失敗。その後ロンドン、ハワイに語学留学し、そこで新しい価値観を得て、旅人へ。
南米横断の旅から環境問題へ興味を持つ。ガイジンハウスでの生活、バックパーカー、サーカスの仕事をしつつ、バリ島近くの小島でエコ・ビーチリゾート「the sunset gecko」立ち上げ運営に携わる。その後ボルネオでの植林などの環境NGOを巡り、one kitchen設立へ。現在はone kithenを運営しつつ、シェアハウス「大塚たくあん」立ち上げ、ワードプレスによるHP立ち上げ講座など、コミュニティーづくりや社会からの自立支援活動を行っている。